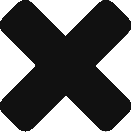鍼灸院を経営する上で、保険請求は収益に大きく関わる重要な業務です。
現在独立を検討されている方や開業して間もない方は、保険請求の仕組みや請求の手順について、不安に思う部分もあるのではないでしょうか。
そこで当記事では、鍼灸院で行った施術に関する保険請求について解説します。
請求の仕組みや手順、療養費支給申請書(レセプト)の書き方などについて詳しくお話ししています。
最後まで目を通すことで、鍼灸院における保険請求を詳しく把握でき、スムーズな形で日々の業務に取り入れられるでしょう。
鍼灸院で保険請求は可能?
現在、鍼灸院を経営されている方であればご存じとは思いますが、鍼灸院での施術では保険請求が可能です。
ただし保険治療の対象になるためには、以下の2つの要件をどちらも満たす必要があります。
1つ目は「保険治療の対象となる傷病であること」です。
神経症やリウマチなどが対象の疾病にあたります。詳しくは次項で紹介していきますが、慢性的な痛みや、病院での治療で完治できなかった症状が対象となります。
2つ目は、「医師が施術に同意していること」です。
担当する医師がまず治療を行った上で、他に有効な施術手段がないなどの正当な理由があり、さらに鍼灸師による施術を許可した場合にのみ保険治療が適応されます。つまり初回申請時には、医師の同意書が必要な旨を留意しましょう。
接骨院・整骨院での保険請求とは異なる点があるので、あらためて把握しておいてください。
参考:接骨院・整骨院で保険診療を行う注意点〜不正請求にも要注意〜
【注意】医療機関との併給は認められない
鍼灸院における保険請求での注意点は、医科診療との「併給」が認められないことです。
併給とは、同一部位、同一症状の傷病に対し、柔整や鍼灸からの請求と医科からの請求が同時になされた状態です。この場合、医科の請求が優先され、はり・きゅうの施術は健康保険扱いにはなりません。
通院だけではなく、医師から薬や湿布などを処方された場合も医科併給に該当します。
鍼灸院での保険請求の仕組み・適応疾患について
それでは次に、鍼灸院での保険請求の仕組みや種類、適応疾患について解説していきます。

保険請求の仕組みとは?
保険請求とは、医療機関や被保険者が立て替えた療養費を請求することを指します。
日本では公的な医療保険制度として国民皆保険制度が採用されており、日本国内に住むすべての人が、国民健康保険か社会保険のいずれかへ加入することを義務付けられています。
医師から施術が必要と診断を受けた場合に限り、保険者に対し鍼灸院での療養費を請求することが可能です。
患者さんが支払うべき療養費は、診療報酬全額のうち最大3割です。残りの7割以上は、医療機関もしくは被保険者が一時的に立て替え、最終的には健康保険組合や市区町村などの保険者が負担することになります。
保険請求は、原則として患者さんご自身で行わなければなりません。「療養費支給申請書」を保険者に提出し、審査の後に立て替え分が支払われます。
鍼灸院が申請を行う場合、療養費支給申請書に患者さんの自筆署名が必須です。やむを得ない場合は鍼灸師による代筆が認められていますが、その場合には患者さんの拇印か印鑑が必要となります。
ご家族の代筆は認められていない点に注意してください。
保険請求の種類
療養費について保険請求することを療養費支給申請といい、主に2通りの方法があります。
一つは償還払いです。
償還払いは、患者さんが療養費の全額を鍼灸院に支払い、自己負担額を除いた療養費を保険者に直接請求する方法です。療養費を立て替える経済的負担や、患者さん自身が慣れない手続きを行う負担などの問題があります。
もう一つが受領委任払いです。
患者さんは自己負担分のみを医療機関窓口で支払い、残りの療養費は鍼灸院が患者さんに代わって療養費の請求を行います。厚生労働省の通達により平成31年1月1日から正式に導入されました。
導入以前からも保険者ごとの判断で行われていましたが、現在は共通の取り扱いとして制度化しています。受領委任の取扱いを希望する鍼灸院は、地方厚生(支)局への申請が必要です。
受領委任払いの取扱いは保険者によって異なります。受領委任制度に参加せず、鍼灸院の保険治療については償還払いのみで療養費を支給する団体もあるため、各保険者のホームページなどで事前に確認しましょう。
鍼灸院での保険適応疾患とは?
鍼灸院での保険治療が認められる疾患は主に次の通りです。
・神経痛(臀部、足先の痺れを伴う坐骨神経痛)
・リウマチ(慢性的な関節痛みや動かしづらさが伴う)
・腰痛症(慢性の腰痛)
・五十肩(慢性的な痛みがあり腕が上がらないなど)
・頚腕症候群(頚から肩、腕にかけて痛みや痺れなど)
・頚椎捻挫後遺症(自動車事故によるむち打ち症)
慢性的な痛みや、医師による施術で改善できなかったものが対象となり、急性の痛みについては適応外となります。
鍼灸保険施術で算定できる料金(療養費)は?

鍼灸施術に保険適用となった際に、算定できる料金(療養費)を把握しておきましょう。
まず、初回施術では初検料を算定できます。
「はり」「きゅう」いずれかを用いた施術の場合は1,780円、はりきゅうを併用した場合は1,860円です。
そして、1回の施術では、はり施術・きゅう施術いずれかで1,550円、はりきゅうを併用した施術では1,610円となります。
また電気を用いた施術(電気鍼など)を行った際は、電療料として34円が加算されます。
加えて、往診(訪問鍼灸)を行う場合、往診先までの距離が片道4キロ以内なら2,300円、4キロ以上なら2,550円が算定可能です。
その他には、施術報告書交付料として480円が算定できます。
【鍼灸院】保険請求をするための準備
ここから鍼灸院で保険請求のための準備について、必要な各書類の解説と、請求までの大まかな流れについて説明します。
施設所開設届を提出
新規で鍼灸院を開設した場合、10日以内に「施設所開設届」の提出が必要です。施設の所在地を管轄する地方厚生(支)局に対し、必要書類を添付の上申請しましょう。
提出書類は以下の通りです。
①施術所開設届(あはきと柔道整復両方を申請する場合、それぞれの届が必要です)
②施術者免許証写し(確認と証明のため原本も持参します)
③施術所の平面図
④最寄の交通機関から施術所までの案内図
※必要書類は各自治体により一部異なる可能性があります。申請前に必ず事前相談を行ってください。
開設届が受理された後に施術所への立ち入り検査が行われ、問題がなければ副本が交付されます。
また、出張訪問専門の鍼灸院の場合、開設届と施術者免許証の写しのみで開設可能です。したがって、基本的に立ち入り検査は行われません。
なお、保険の取扱開始日は「開設届を提出した当日」からですので覚えておきましょう。
受領委任の取扱いを地方厚生(市)局に申請
平成31年1月1日から、鍼灸院などのあはき(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう)施術者が受領委任による保険請求を行うためには、地方厚生(支)局への届け出が必要となりました。必要な書類は以下の通りです。
必要な様式
①確約書
②療養費の受領委任の取扱いに係る申出(施術所の申し出)
③療養費の受領委任の取扱いに係る申出(同意書)
添付書類
①施術所の開設届・変更届・出張業務開始届の写し
②免許証の写し(施術管理者以外に勤務する施術者を含む)
③施術管理者選任等証明(個人か法人で様式が異なる)
④勤務形態確認票(複数管理・複数勤務の場合)
⑤住民票(施術管理者が出張専門施術者の場合)
※必要書類は各自治体により一部異なる可能性があります。申請前に必ず事前相談を行ってください。
登録記号番号の取得
受領委任の申請が承諾されると、地方厚生(市)局から10桁の登録記録番号が付番されます。
附番された登録記録番号は、保険者に対して申告する必要があります。
医師の同意書をもらう
療養費の支払を受けるためには、事前に保険医の同意書が必要となります。
同意期間は6か月です。6か月を越えても引き続き施術が必要な場合は、患者さんが再度保険医の診察を受けた後、再同意の文書と併せて施術報告書の添付が求められます。
領収書の作成
償還払いのみ受け付けている保険者に対しては、患者さん自身が請求手続きを行う必要があります。
請求には領収書原本の添付が必要です。領収書には全額自己負担の旨を記載の上施術日を記入、領収印を押印してください。
レセプト用紙の記入
療養費支給申請書(レセプト)の記入を行います。
患者さんから署名をいただく際は、保険証の内容が変わっていないか必ず確認してください。資格喪失がないか、保険者が変わっていないか等のチェックをします。
保険者が同一でも記号・番号が変わっているケースがあるため注意が必要です。また、患者さんが扶養に入っている場合、患者さん本人ではなく被保険者の署名が必要であることを覚えておきましょう。
また、レセプトと併せてカルテの記入も義務付けられているので、忘れずに記入してください。
参考:
接骨院・整骨院のレセプト作成はどうすればいい?保険請求する際の流れや方法を解説します!
鍼灸院にカルテは必要?導入するメリットや電子カルテについて
【鍼灸院】保険請求する際に必要なレセプトの書き方

以下より、保険請求をする際の療養費支給申請書(レセプト)について、各欄ごとの記入方法を解説します。
なお、療養費支給申請書に記載する項目は基本的に共通ですが、書式は各自治体や保険者団体によって異なります。不明点がある場合は発行元にお問い合わせください。
被保険者欄
保険請求を行う際には被保険者本人の署名が必要です。
ただし、患者さんがご家族の扶養に入っている場合など、必ずしも患者さんが被保険者とは限りません。
施術内容欄
患者さんが保険医から同意を受けた傷病名を選んでそのまま転記、あるいは項目に〇印をつけます。当てはまる傷病名が無い場合は「その他」の欄に傷病名を追記してください。
発症・負傷年月日も同意書に記載されている日付を転記します。請求金額は、合計金額より一部負担金を差し引いた金額を記載してください。
往診があった場合は、その費用と距離についても記載します。なお、施術所から訪問先までの距離が片道16km超の場合、往診を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められません。
施術証明欄
登録記録番号と施術管理者の氏名を記入します。同じ患者さんを施術管理者以外、あるいは施術管理者を含む複数の施術者が施術した場合も同様です。署名は施術者本人ではなく必ず施術管理者が行ってください。
なお、施術所を持たない出張専門の鍼灸師の場合、施術所の名称は記入不要です。施術所の所在地は地方厚生(市)局に申し出た自宅の住所を記入します。
申請欄
申請欄には保険者の宛名を記入します。
宛名は保険者機関の長、たとえば保険組合の理事長や市長です。日付については、当月分のすべての施術が終わった後に記入してください。
支払機関欄
取引金融機関名を入力します。
保険者によっては支払区分が「振込のみ」などと指定されている場合もあるため、初回の場合は事前に問い合わせてください。
同意記録欄
初回診療で保険医による同意書の原本を添付する場合、同意記録欄の記入は不要です。
初回以降、前月分以前に同意書の原本を添付している場合は、同意書の内容をもとに同意記録欄に記入します。
摘要欄(往診理由の説明等)
他の欄に書ききれなかった追加事項がある場合、摘要欄に追記します。追記の例としては「施術者が複数いる場合」「16km超の往診があった場合」などです。
施術管理者以外に施術を行った場合、第一施術者、第二施術者の氏名を記載して捺印します。施術日も忘れずに記入します。
往診先が鍼灸院からの距離が16km超の場合、施術が必要な説明を記載してください。
参考:レセプトが返戻されてしまう理由とは?返戻理由と対策、再請求について徹底解説します!
鍼灸保険施術のメリット・デメリット

保険を使った鍼灸施術には、メリット・デメリットの両方が存在するといえます。
メリットとしては、施術料金が低いことで利用者が増えやすい点です。また料金が安ければ、継続率も高くなるのは言うまでもありません。
デメリットは手続きが複雑である点や適用疾患が限られていることと、なんといっても「医師が同意書を書いてくれない可能性がある」点です。
『これから開業して保険を取り入れていこう』と考えている鍼灸師の方は、保険施術の良い点と悪い点をそれぞれ把握しておきましょう。
自費施術の比重を増やしていくことがおすすめ
鍼灸施術における保険適用の範囲は、指定された傷病のみが対象で、さらに医師の同意書が必要になります。
また、整骨院や接骨院では1施設あたりの療養費が年々減少しており、鍼灸院でもいつ療養費の削減が行われるかわかりません。
今後、保険治療のみに頼った鍼灸院で、安定的な経営を行っていくのは困難になるのではないでしょうか。
安定的な鍼灸院経営を行っていくためには、保険請求のみに頼るのではなく、自費治療と合わせてサービスを提供していくことが大切です。自費診療なら、専門性を有することで競合の鍼灸院との差別化が計りやすくなります。
たとえば最近では、美容鍼とよばれる女性向けの施術が注目されており「生理痛の解消」「ダイエット」「顔のしわ解消」「リフトアップ」など、主に女性の中でも高所得者層をターゲットにした鍼灸サロンが話題になっています。
美容鍼は客単価が高いため、お客様をしっかりと集客できれば高単価のサービスを提供できるのも魅力的です。
また、鍼による疼痛減少の後に根本原因に対する施術や予防の観点から、ストレッチやトレーニングなどの運動療法も注目されています。その結果、よりお客様と長期的な接点を構築していくことになり、自院の売上げに貢献できるのがポイントです。
保険治療に頼らずに安定な施設運営をしたい経営者にとっては、今後も自費サービスの需要が高まるのではないでしょうか。
参考:整骨院・接骨院の自費メニューの作り方!料金設定や回数券についても解説
鍼灸院での保険請求に関するまとめ
鍼灸院の保険請求について、概要から申請方法までをまとめました。
はり・きゅうによる施術の場合、保険適用の範囲が限定的かつ厳しく定められています。請求トラブルやレセプトの返戻を避けるためにも、正しい知識を身につけておくことをおすすめします。
なお、自費移行への関心は高まっていますが、メニューを作成する際は目的と費用対効果を考え、しっかりとした根拠をもとに検討するようにしましょう。
〈参照元〉
厚生労働省 | はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ
厚生労働省 | はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任を取り扱う保険者等について
厚生労働省保健局医療課 | はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について