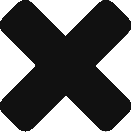問診票は初診患者との信頼関係を築くうえで、欠かせない重要書類です。症状や生活習慣を正確に把握し、最適な施術方針を導き出すための基盤であり、同時にトラブル防止や個人情報保護にも関係します。
この記事をご覧いただくことで、接骨院の問診票の基本構成から作成手順、質問項目の設計、記入例、さらに改善のポイントまでを体系的に理解できます。
これから開業を予定している方はもちろん、既存の問診票を見直したい方にとっても、実践的に役立つ内容です。ぜひ最後までご覧ください。
接骨院・整骨院の問診票とは
接骨院・整骨院の問診票は、患者の症状や生活背景を正確に把握し、最適な施術方針を立てるための基本資料です。単に情報を記入するための書類ではなく、患者との信頼関係を築くための重要なコミュニケーションツールとして機能します。
初診時に「どんな悩みを抱えて来院したのか」「どのような生活習慣が影響しているのか」を丁寧に聞き取ることで、施術の方向性を明確にし、満足度や再来率の向上にもつながります。
また、問診票はカルテ作成や保険請求の基礎資料としても欠かせません。個人情報保護法などの法的観点からも、記載内容の明確化と保管ルールの遵守が求められます。特に接骨院・整骨院では健康保険や自賠責保険を扱う場面が多く、施術同意書との整合性を保つことが信頼性の確保につながります。

接骨院・整骨院の問診票を作成する前に確認すべきポイント
問診票を作る際、いきなりフォーマットを整えるのではなく、まず「目的」と「活用方法」を明確にすることが大切です。院の方針や施術対象に合わせて、どのような情報を得たいのかを整理しておくと、後の記入負担や改訂の手間を減らせます。
問診票を作る際、まず意識すべきは「どんな目的で」「誰が使うのか」という視点です。ここでは、作成する前に確認すべきポイントをご紹介します。
■目的設定を最初に明確にする
問診票には大きく分けて次の2つの目的があります。
- 診療・施術に必要な情報を正確に収集すること
- 患者との信頼関係を構築すること
この2点のどちらかが欠けると、形だけの書類になってしまいます。特に初診患者の場合、「話を聞いてもらえた」という印象を与えるだけで満足度が上がります。
■院の方針に沿った質問設計
院によって得意分野(スポーツ障害、慢性痛、交通事故など)が異なるため、治療方針と一致する設問を設けることが大切です。
たとえば、姿勢・仕事姿勢に関する質問を多く設ける院もあれば、睡眠・運動習慣を中心に聞くケースもあります。
■個人情報保護と記載ルール
個人情報は、第三者提供や保管期間を明示し、患者の署名を得ておく必要があります。特に電子化する場合は、アクセス権の管理が不可欠です。
接骨院・整骨院の問診票の作成手順
問診票の内容は、患者・スタッフ双方にとってわかりやすく、無理なく記入・運用できる構成にすることが重要です。問診票作成の流れは、「基本情報 → 症状 → 既往歴 → 生活背景 → 同意項目」という順序が一般的です。
ここでは、現場で使いやすくミスの起こりにくい問診票を作るための5つのステップを紹介します。
ステップ1:基本情報欄を設計する
「 患者氏名年齢」「住所」「電話番号」「職業」「来院経路」などを記入する欄を設けます。「保険証番号」や「紹介元」を記載する項目を追加しておくと、事務処理がスムーズになります。
ステップ2:症状や発症経緯を聞く項目を作る
「どの部位が痛いか」「いつから痛いか」「どんな動作で痛むか」を明確に記載してもらいます。人体シルエットの図を印刷して記入してもらう形式も有効です。視覚的に伝わりやすく、スタッフの共有も容易になります。
ステップ3:既往歴・通院歴を確認する
「これまでに整形外科・整骨院などに通院した経験」「服薬・手術歴」「既往症」などを記入します。重複施術や禁忌行為を避けるために欠かせません。
ステップ4:生活習慣・仕事環境などを把握する
姿勢・運動習慣・睡眠・仕事内容などを聞き取り、原因分析に活用します。長時間のデスクワークや肉体労働など、生活環境が痛みを左右するケースは少なくありません。
ステップ5:同意・注意事項の項目を入れる
治療内容や個人情報の取り扱いについて同意を得る欄を設けます。「施術は治療目的であり、医療行為ではありません」などの文面を添えることで、トラブル防止になります。
接骨院・整骨院の問診票に入れるべき質問項目リスト
どの質問を必須にするか、任意にするかは、院の方針や患者層によって異なります。ここでは、基本構成を保ちつつも、効率的に情報を集められる質問項目を分類表として整理します。
自院の特色に合わせて取捨選択しましょう。
【問診票に入れるべき質問項目分類表】
| 分類 | 質問項目 | 内容例 | 目的 |
| 必須項目 | 氏名・生年月日・住所・連絡先 | 基本情報の確認 | カルテ作成・保険請求 |
| 主訴・症状 | 「どの部位が痛い」「いつから」 | 施術内容の判断材料 | |
| 発症原因 | 「事故」「スポーツ」「姿勢」 | 法的対応・施術方針決定 | |
| 既往歴・服薬 | 「過去の病気」「服薬中の薬」 | 禁忌行為の回避 | |
| 同意欄・署名 | 施術内容・個人情報の同意 | リスク管理 | |
| 任意項目 | 職業・勤務形態 | 「デスクワーク」「立ち仕事」 | 生活習慣分析 |
| 睡眠・運動・食生活 | 「睡眠時間」「運動頻度」 | 体調の背景理解 | |
| 来院目的・期待 | 「早く治したい」「メンテナンス」 | モチベーション確認 | |
| 精神的ストレス | 「仕事のストレス」「家庭」 | 痛みの心理的要因分析 | |
| 来院経路 | 「紹介」「ネット検索」 | マーケティング活用 |
この分類を基準に、自院の特徴に合った項目を取捨選択するのがおすすめです。たとえばスポーツ障害専門院なら、運動内容・ポジションなどを細かく設定。
交通事故対応院なら「保険会社」「事故日」「病院併用の有無」などを追加します。
接骨院・整骨院の問診票の記入例・書き方のコツ
どれほど丁寧に設計された問診票でも、患者が書きづらければ意味がありません。ここでは、実際の記入例を交えながら初診・再診・事故対応など、場面ごとのポイント解説と、書きやすく・読みやすい問診票を作るためのコツを紹介します。
問診票は「患者がスムーズに書けること」と「スタッフがすぐ理解できること」の両立が重要です。特に接骨院では、保険診療・自費施術・事故対応など状況が多様なため、目的別の書式を用意するのも効果的です。

記入例①:初診のケース
初めて来院した患者にとって、問診票は「院の第一印象」を決める書類です。この段階では、過剰に専門的な質問を避け、「痛みの場所」「いつから」「どんな時に痛むか」「どんなことを期待しているか」といった基本情報に集中させましょう。
【記入例】
- 症状:右肩を上げると痛みがある。2週間前から。
- きっかけ:荷物を持ち上げた際に違和感。
- 通院歴:なし。
- 希望:仕事に支障があるため、早く改善したい。
このように、患者が自分の言葉で書ける質問形式「はい/いいえ で終わらない設問」が理想です。
記入例②:再診・継続通院のケース
再診時は「前回からの変化」を中心に設問を構成します。
【例】
- 痛みの強さはどの程度変化しましたか?(10段階評価)
- 改善を感じる動作・痛みが残る動作は?
- 通院頻度に無理はありませんか?
このように、「前回→現在→次回」に一貫性を持たせることで、治療計画の精度が向上します。
記入例③:交通事故・保険対応のケース
事故対応時の問診票は、法的トラブル防止の観点からも極めて重要です。
次のような項目を明確に記載します。
- 事故発生日時・状況(相手車両の有無・警察届出の有無)
- 病院受診歴・診断名 – 保険会社名・担当者連絡先
- 他院との併用有無(整形外科・整体など)
上記のような情報が正確に残っていないと、保険対応の際にトラブルが発生するリスクがあります。
また、施術同意書を必ず添付し、施術内容・目的を明記しておきましょう。
接骨院・整骨院で問診票を改善するためのポイント
作成した問診票は、一度作って終わりではなく、定期的に見直すことが重要です。患者の傾向や治療メニューが変わると、必要な情報も変化します。ここでは、現場で活用できる「改善チェックリスト」を使って、改善の方向性を明確にします。
問診票の改善は、患者・スタッフ・院の三方向の視点で行うのが基本で、「患者にとって書きやすいか」「スタッフにとって処理しやすいか」「院の目的に合っているか」をそれぞれ検証します。
問診票改善チェックリスト
| チェック項目 | 内容 | 改善のヒント |
| 患者が書きやすいレイアウトか | 文字が小さすぎない・余白がある | フォントは12pt以上、1ページ内に収まる構成 |
| 設問が多すぎないか | 10分以内で記入できる量か | 不要項目は年1回見直し |
| 記入ミスが多い項目はないか | 空欄・誤記が頻出していないか | 選択式に変更・補足説明を追加 |
| スタッフが確認しやすいか | 回答の読み取り・入力が容易か | チェック欄の配置を統一する |
| 法的記載が漏れていないか | 同意文・署名欄は明示されているか | 弁護士・社労士監修を検討 |
| 院の強みを反映しているか | 得意施術や理念が伝わる内容か | PR項目や紹介欄を追加 |
| 定期的に更新されているか | 最終改訂日が明記されているか | 半年〜1年ごとにアップデート |
このようなチェックをもとに、「今の問診票が患者視点に立てているか」を評価しましょう。問診票の改善は、患者満足度の改善=経営改善にもつながります。
接骨院・整骨院におけるWeb問診・デジタル化の活用
最近は、紙の問診票からタブレット・スマートフォンで入力する「Web問診」への移行が進んでいます。ここでは、Web問診の仕組みや導入の流れ、注意すべき個人情報保護のポイントを具体的に解説します。
紙の問診票は、記入漏れ・読みにくさ・転記ミスといった問題が生じやすいのが難点です。一方でWeb問診では、患者が事前にスマートフォンなどから入力でき、受付での待ち時間を短縮できます。さらに、電子カルテとの連携により、スタッフの入力負担も軽減されます。
■デジタル化導入のステップ
Web問診や電子問診を導入する際は、単に紙の内容をデジタル化するだけではなく、院内の運用体制やセキュリティ面までを含めた準備が重要です。
- Web問診ツールを選定する(クラウド型・アプリ型など)
- 既存の紙問診票を電子フォーム化(Googleフォーム等で試験運用も可能)
- 個人情報保護対策を設定(通信暗号化・アクセス制限)
- スタッフ教育を実施(入力サポート・説明方法の統一)
■導入のメリット
Web問診や電子問診の導入におけるメリットは、特に下記のような点が挙げられます。
- 待ち時間短縮・受付業務の効率化
- 患者情報の自動集計・分析
- 記入ミス・転記ミスの防止
- 感染症対策(非接触対応)
このように、Web問診を上手に活用すれば、スタッフの負担を軽減しながら、患者満足度とリピート率の両方を向上させることができます。
■注意点
Web問診では、端末操作に不慣れな患者への配慮が必要です。高齢層が多い地域では、紙と併用する「ハイブリッド運用」が望ましいでしょう。

まとめ:接骨院・整骨院の問診票は「患者との信頼関係」を築く第一歩
問診票は、患者の声を最初に受け取る大切なコミュニケーションツールです。正確な情報収集に加えて、安心して通える信頼感を与える役割も担っています。最後に、この記事の要点を整理して振り返りましょう。
接骨院の問診票は、症状を把握するための単なる紙ではなく、「患者理解」と「信頼構築」のための出発点です。
- 目的を明確にし、院の方針に沿った質問を設定する
- 患者が書きやすく、スタッフが扱いやすい設計にする
- 定期的に見直し、改善チェックリストで検証する
- デジタル化で業務効率を上げる
問診票を整えることは、治療効果を最大化するだけでなく、接骨院の経営基盤を強化する行為でもあります。日々の現場で改善を重ねながら、「書かせる問診」から「信頼を築く問診」へと進化させていきましょう。